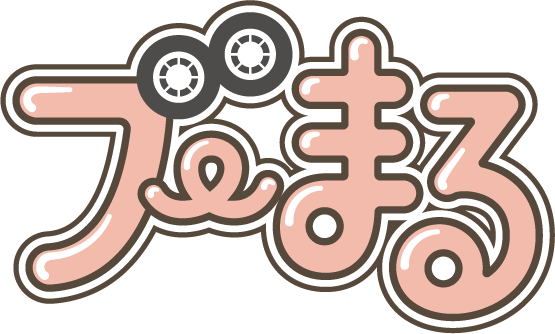雪道のような路面状況では、怖い思いをするなど、快適なドライブと呼ぶには程遠いかもしれません。
徒歩でも雪道を転ぶことなく安全に歩くのは難しいのに、クルマの運転なんて…とはいえ、雪道でも通勤など外出しないといけない場合もあるでしょう。
確かに雪道はリスクがありますが、大事なのはそのリスクとどうやって付き合っていくかです。
雪道の特性や危険性を正しく理解すれば、雪道のドライブに対するハードルは低くなるはずです。
雪道の特性を知ることから始めよう

雪道の走行は危険が伴うことは、初心者の方でも理解できると思います。
具体的にどういう理由で危険なのか?普段とは違う雪道の特性を見てみましょう。
雪道の特性
視界が悪くホワイトアウト現象も
空気中に細かい粒子などが舞っている状態であれば視界不良になるのは想像しやすいですよね。
冬でなくても雨、霧、砂埃などで視界不良になることもあります。
雪の場合は、周りにある物にも付着することで視界に映るものが全て真っ白になる、いわゆるホワイトアウト現象が発生しやすくなります。
景色が全て白一色になり、境目がわからなくなるので方向感覚などが失われることに。
進まない・止まらない・曲がらない
クルマは走る、止まる、曲がるの3要素があって安全な走行が可能となります。
安全な走行を確保しているのは、タイヤと路面との摩擦。
雪は細かい氷の粒なので、集まると氷の塊となってしまいます。
表面が滑らかな氷の上でタイヤが普段通りの摩擦力(グリップ力)を確保できるわけはなく、摩擦力の低下によってクルマは思うように進まない、止まらない、曲がらないとなってしまうのです。
ノーマルタイヤはNG!スタッドレスが大前提
ノーマルタイヤ、いわゆるサマータイヤ、夏用タイヤは雪道では全くグリップ力を発揮しないもの。
ノーマルタイヤは、アスファルト舗装路で摩擦係数が高くなるように設計されているので、表面は意外とツルツルとしています。
ノーマルタイヤのツルツルとした表面は、アスファルトでは有効ですが、雪道では逆効果に。
路面にもタイヤにもお互いに引っ掛かる部分が少ないので滑ってしまうわけです。
一方、冬タイヤであるスタッドレスタイヤは、柔らかいゴムにサイプと言われる細かい溝がいくつも切られており、ゴム自体も発泡ゴムやクルミの殻を配合するなどされています。
つまり細かい凹凸がタイヤ側にいくつもあり、雪道に対しての引っ掛かりになっているのです。
駆動方式での違い
タイヤのグリップ力には限界値がありますが、普段の路面状況でその限界値を使い切る走行というのは稀です。
ところが雪道で摩擦力が低下すると、低速であっても簡単に限界を迎えることに。
タイヤのグリップ力を100%とした場合、グリップ力は駆動力(アクセル)、制動力(ブレーキ)、コーナリングフォース(ハンドル)、のそれぞれに振り分けられます。
アクセルを踏みながら曲がろうとしたときに、グリップ力を超えるハンドル操作をしても、超えてしまった分タイヤはスリップして摩擦力を失います。
これが駆動方式によってどのタイヤが先にスリップするかの違いとなり、車全体の挙動の違いとして現れます。
FR車の場合は駆動力は後輪に伝えられています。つまりアクセルの踏み込みによってグリップ力を常に使っています。
アクセルを踏んだ状態で更にハンドル操作が加わると、先にグリップ力の限界を迎えるのは後輪となります。
これがハンドルの舵角以上に曲がってしまうオーバーステアのスピンに繋がります。
FF車の場合は逆に前輪で駆動していますし、タイヤの舵角操作というのは前輪で行うもの。
アクセルとハンドル操作を同時に行ったときに、最初にグリップ力を失うのは前輪です。
ハンドルの舵角よりも外に膨らんでいくアンダーステアの状態になります。
[AdSense-kiji]
雪道を安全に走行するポイント

雪道の走行にリスクがありますが、だからと言って車を利用しないわけにもいきません。
リスクがあることを正しく理解し、リスクをできる限り回避する事を心がけることで、雪道でも安全に走行できるようになります。
安全走行のポイント
雪をしっかりと落とす
雪道を走行する前に、まずは車体についた雪を落としましょう。
ガラスについたものはもちろんのこと、ヘッドライトやフロントグリル付近、ルーフの上の屋根雪もです。
視界不良になった時にヘッドライトが使えなければ困りますし、雪がラジエーターを塞いでしまうとオーバーヒートの原因にも。
ルーフの上の屋根雪は走行中に落ちてくるので、フロントガラスの視界を遮ったり、後続車への落下したりすることになります。
低速でABSの動作確認
路面の凍結が予想される場合には、事前に交通量の少ない場所において低速でのブレーキの利き具合をチェックすると良いでしょう。
ABSが装備されている車両は、摩擦の低い凍結路面などではその作動が良く分かります。
ブレーキを踏むことによって、油圧を発生させるためのポンプが作動し、発生した油圧の一部がブレーキペダルを跳ね返してくるのです。
ブレーキペダルに振動や音として伝わってくるのであれば、ABSは正常に作動しています。
雪道でのブレーキの踏み方
雪道などのスリップしやすい路面でのブレーキはポンピングブレーキが有効ですよね。
ポンピングブレーキは、数回に分けてブレーキを踏みタイヤをロックさせずに徐々に停止するものですが、ブレーキランプを点滅させることで後続車への合図にもなります。
前方の車両から大きく間隔を開け、早めのポンピングブレーキによって徐々に減速を行うのが良いでしょう。
ABSを過信しすぎるのは問題ですし、なによりABSを本気で作動させたときの振動や音というのは非常に不快なもの。
併せてエンジンブレーキも使えるのであればベストです。
ABSは雪道における緊急回避として、短い制動距離で確実に停止したい場合には作動させましょう。
思いっきりブレーキを踏み込んでABSを作動させるの方が確実に短い制動距離で止まれますし、タイヤがロックしていないのでハンドル操作もある程度受け付けてくれます。
大きな音や振動が伴いますが、ABSが正常に動作している証拠でもあるので、臆さずブレーキを踏み続けてください。
車間距離を大きくとる
雪道になると交通全体が低速走行になってくるので、つい車間距離は短くなってしまいます。
確かに速度は遅いのですが、凍結した路面ではスタッドレスタイヤでも確実に止まってくれる保証はありません。
また前方の車が雪によって思わぬ動きをする可能性も。
車間距離はいつも以上に大きくとることで、不測の事態に遭遇しても対処する余裕が生まれます。
車線変更は控えめにする
雪道ではタイヤによって路面に溝ができる轍が発生します。
この状態で車線変更をするのは、その轍の高さの雪を乗り越えることを意味しています。
雪で出来た轍はタイヤの動きを妨げますし、乗り上げる際には車両が傾きます。
摩擦の低い路面でその様な操作をすると車両が思わぬ挙動をすることがあるので、車線変更は最小限かつ控えめに行うようにしましょう。
幹線道路を中心に走る
幹線道路ともなれば交通量も多いですし、雪の影響で渋滞も発生しやすいです。しかし、渋滞していない裏道を安易に選ぶのは危険です。
幹線道路は除雪作業が優先的に行われる道路であるのに対して、その他の道路は除雪が後回しになっています。
それだけ雪が深いこともあり、スタックする可能性も高いです。
万一スタックした場合、幹線道路上でスタックしたのであれば、周りの車両から手助けしてもらえる可能性もありますが、交通量の少ない道路では一人で対処するしかありません。
軽自動車と普通車で走り方は違う?
軽自動車は普通車に比べると軽量でコンパクト。小回りも利いて曲がりやすいですし、雪で道幅が狭くなった道を走る分には有利です。
ただし軽量であるため道路上にできた凸凹や轍ではバウンドしやすく、乗り心地としては不安定な感じはします。
普通車の場合は軽自動車とは逆で、道幅が広い場所である必要はありますが、重量があれば雪で出来た轍も潰しながら走行しやすく、乗り心地という意味での安定性はあります。
ただし重量が重くなるほど雪道ではブレーキが利かなくなり、スリップも起こしやすいです。
走破性という点で雪道をスムーズに走れるクルマのタイプは「4WDの軽トラック」になります。
軽量ですし、最低地上高も確保されていてスタックしにくいです。
雪道走行で準備しておくと便利なもの
2020年2月27日(木)
AM10:00よりチェーン規制にて営業開始致します。
写真のように日陰は 路上に雪が残っております。
スリップに注意してください。
スタッドレスタイヤ又はチェーン装着車のみ通行可です。mh#芦ノ湖 pic.twitter.com/M6btFENRbY— 芦ノ湖スカイライン (@SkylineAshinoko) February 27, 2020
雪道への備えをしておくと、いざという時に助かりますよね。
雪が降っているわけですから、車に積もった雪を除雪するための「除雪ブラシ」は必要です。
車の周りを除雪するには「スチール製のスコップ、ショベル」があると、凍った雪を割るのにも便利。
また除雪作業の際に濡れてしまう手足に対して「防水手袋」や「長靴」があると作業がしやすくなります。
スタックした場合の脱出用品として「専用の脱出マットや脱出プレート」があり、タイヤで踏むことでスタックからの脱出を補助できます。
さらに「タイヤチェーン」はチェーン規制となった道を走るうえで必要に。
チェーン規制がかかった高速道路などでは、スタッドレスタイヤやオールシーズンタイヤだけでは走ることはできず、必ずチェーン装着車でなければなりません。
チェーン規制となる場所の手前にはチェーン脱着所やサービスエリアがあるので、そこで装着するようにしましょう。
いざという時の連絡手段と連絡先の確認もしてください。
携帯電話のバッテリー切れなどに備えて車内で使える充電器やモバイルバッテリーがあると良いですね。
連絡先はロードサービス関係。事故やスタックした場合には、最寄りのレッカー業者やJAFに救援の依頼をしますし、任意の自動車保険にロードサービスが付帯されていれば、保険会社に連絡すれば手配をしてくれます。
その他、バッテリー上がりに対して「ジャンプスターター」や、立ち往生に対して「簡易トイレ」などがあると良いでしょう。
短時間でバッテリー上がりを復活

[AdSense-kiji]
雪道は走り慣れた場所でも危険がある

普段走り慣れている道路であっても、雪道は別。
雪によって滑りやすく路面事態も凸凹していますし、走り難い状態になっています。
慣れているからなどとは考えず、走る道路の状況をよく観察するようにしてください。
危険な箇所
坂道
雪が降った状態での坂道はスリップする危険性が高まります。
上り坂の途中で止まったらスタックした、下り坂で止まれなくなったというのはよくある話。
上り坂ではできる限り止まることなく、坂の終わりまで一気に登りきることを心がけてください。
下り坂ではエンジンブレーキを利かせて、低速で下ることを意識しましょう。
カーブ
カーブではハンドルを切るしかないわけですが、ハンドルを切るとタイヤのグリップ力を失ってスリップする可能性があります。
カーブでハンドル操作中にアクセルやブレーキを踏むほど、グリップ力が必要になってしまいます。
重要なのは、雪道によって低下しているグリップ力をどのように使うかです。
以下の2点を注意することで、タイヤのグリップ力をコーナリングに集中させられます。
- カーブに入る手前で十分に減速する
- 旋回中はハンドルの操作に重点を置いてアクセルとブレーキはあまり使わないようにする
交差点
交差点はm対向車とのすれ違いや、歩行者の横断などがある場所。
操作しずらい雪道で判断を誤ると事故につながるので注意しましょう。
普段のタイミングなら右折できると思っても、急激なアクセル操作はタイヤをスリップさせます。
対向車のタイヤもまたスリップしやすいので止まることができません。
交差点ではとにかく焦らず余裕をもって通過することが大事なのです。
トンネル
トンネルの中は雪がないアスファルトの乾燥路面。しかし出入り口は雪や凍結路面に切り替わるポイントでもあります。
前後のタイヤがそれぞれ違った摩擦係数の路面の上を走ることは、駆動力のバランスが崩れることも意味しています。
急激なグリップ力の差が生じると、車両がスピンを起こす場合もあるので覚えておきましょう。
橋の上
橋は上下に空間があって、風が通り抜ける構造になっています。そのため橋の上の路面は温度が低く、凍結路面となりやすい場所です。
陸地になっている道が凍結していなくても、宙に浮いている橋の上は凍結していることもある…これはトンネルの出入り口と同じ状態となります。
日陰
日陰もまたトンネルや橋の上と同様です。
同じ雪道であっても、日に当たって溶けている場所と溶けていない場所の差が生じており、それぞれ摩擦係数が違います。
特に溶けて水分を含んだ凍結路面は滑りやすいですので、日が高い時ほど注意が必要です。
雪道のタイプによって走り方や注意点も変わる?!

雪道と一言でいっても、実際にはその状態は様々。
雪道の状態が変われば、それに対する走り方や注意点も変わってきます。
雪道の状態
新雪
雪が降って間もなく、車の通行によって押し固められていない状態です。
雪を踏みしめながら走行することになり、路面が凍結しているわけではないので、スリップはしにくいといえます。
ただし雪が深いところに入ると、車が雪の上に乗り上げる亀の子状態になってスタックすることも。
亀の子状態のスタックを回避するには車の最低地上高が確保されていることが大事です。
荷物を積むことで車高が下がることも念頭に入れておきましょう。
また風があると積もっていた雪が再び舞い上がる地吹雪となり、ホワイトアウトを起こしやすい状態であるとも言えます。
圧雪
雪道の多くの場合が、雪が踏み固められて轍ができている、圧雪状態です。
雪がそのまま固まったものなので道路上の凸凹が目立ち、窪みにタイヤが嵌ることでスタックしやすい状態です。
またタイヤで磨かれたことにより、局所的にアイスバーンとなっていることもあります。
ミラーアイスバーン
溶けた雪が再び凍結した状態がアイスバーンですが、車の往来によって磨き上げられて鏡の様に滑らかな平面の状態になったものです。ミラーバーンとも言われます。
圧雪に見られる局所的なアイスバーンとは異なり、凸凹もなくて一見すると綺麗な路面で走りやすいように見えますが、それだけ摩擦が少なくて止まれないという事を意味しています。
ブラックアイスバーン
アイスバーンの中でも氷の層が薄いもの。
アスファルトの色が透けてわかるほどに薄い氷で出来たアイスバーンで、一見すると濡れた路面にしか見えません。
スピードもつい出してしまう傾向にあり、アイスバーンであることにドライバーが気が付き難いです。
この点がブラックアイスバーンが最も危険と言われる要因となっています。
雪道走行でよくあるアクシデント

雪が降ることによって交通はマヒしますし、様々なアクシデントが発生します。
具体的にはどのようなアクシデントが考えられるのでしょうか?
アクシデント
空転して滑ったら?
走行中のタイヤが空転してスリップを起こしているのであれば、減速してグリップ力が回復するのを待つことになります。
ABSが標準装備されている車両についてはブレーキによる減速を重視し、ハンドルは走行レーンを維持する程度の少ない範囲で操作します。
ABS非装備の車両においてはポンピングブレーキによる減速を試みることになります。
オーバーステアによるスピンの回避として、車両が向く方向とは逆にハンドルを切るカウンターステアという方法もあります。
ただ、前輪のタイヤのグリップ力が残っていることが前提で、4輪全てにおいてスリップしている場合には効果がありません。
2012年より横滑り防止装置の装着義務化が始まっており、横滑り防止装置を搭載した車両についてはスリップに対して自動的にブレーキがかかり姿勢を維持するようになっています。
発進時のスタック
走行中のタイヤが滑ってしまった場合はブレーキをかけることになります。
しかし停止している車が発進する際に滑ってしまう…いわゆるスタックの時はどうすれば良いのでしょうか。
まずはスタックした車両の周りの除雪が必要。
雪という高さがある段差を乗り越えようとしている状態なので、その段差を小さくするのです。
新雪の場合であれば踏み固めるというのも効果的。併せてスタック脱出用のマットやプレートなどを駆動輪に踏ませて使うのと良いでしょう。
凍結防止剤や砂などがあるならタイヤの周りに巻いてやると効果的です。
平地でのスタック脱出のコツとしては、前後に車両を動かして雪を踏み固め、勢いを付けて発進するという方法があります。
前後に動かすことで助走するだけのスペースを作るわけです。
またこの方法で脱出を試みる場合は、トラクションコントロールをOFFにします。
多少スピンしながらでも勢いで脱出したい状況なので、スピンを検知するとアクセルを緩めてしまうトラクションコントロールは、スタックした状況では不利に働いてしまうことがあるのです。
バッテリーが上がる
雪が降っている状況であれば気温も低いはず。
気温が低いとバッテリー内での化学反応が促進されず、エンジンを始動するだけの電力を発揮できなくなることもあります。
そのまま放置しているとバッテーリー上がりの原因に。
またエンジンオイルも硬くなるので、始動性を悪化させる要因になります。
車の凍結
車にはエンジンの冷却水やウォッシャー液などが搭載されています。
それぞれには不凍液が添加されており、これによって外気温が0℃以下になっても凍結しないようになっています。
ところが補充の際に、水で薄めてしまうことで凍結温度が上がってしまい、配管内で凍結を起こす場合があります。
またガラス面に霜や着氷するという場合も。この場合、お湯を使うとガラスが急激な温度変化による膨張によって割れることがありますので、お湯を使って溶かすのは避けましょう。
ガラスへの着氷はデフロスターでゆっくりと溶かす以外に、アルコールが添加された解氷スプレーを使う事で、ガラスについた氷を素早く除去できます。
スタッドレスタイヤの劣化
スタッドレスタイヤもタイヤなので摩耗による劣化があります。
溝の深さに対して50%がスタッドレスタイヤとして使える限界とされており、それを知らせるのがスリップサインとは別で刻まれています。
またスタッドレスタイヤが機能するうえではゴムの柔軟性も必要。
スタッドレスタイヤには細かいサイプが刻まれており、そのサイプが機能するためにはゴムが柔軟でなければならないのです。
スタッドレスタイヤは通常の夏タイヤに比べると柔らかく作られていますが、経年劣化によって硬くなり柔軟性を失ってしまいます。
国内のメーカーによってスタッドレスタイヤの作り方や材質などにより寿命には違いがありますが、だいたい4シーズンでスタッドレスタイヤの寿命がくると言われています。
レスキューは直ぐには来ない
雪道で立ち往生してしまうのは1台や2台ではありません。
至る所でスタックを起こし、渋滞が発生することも。こうなるとロードサービスを頼んでも、すぐには現場まで来れないのです。
平成30年豪雪の際には自衛隊の災害派遣もなされましたが、国道8号線の立ち往生解消までに3日を要しています。
レスキューを呼んだ場所が幹線道路であっても、実際に救助されるまでには非常に長い時間を要することもあるのです。
大規模な立ち往生というのは一種の災害なので、その災害に備えて車の中に防災用品やアウトドア用品を積んでおくというのも対処法の一つになります。
防災用品というと水と食料が真っ先に挙げられますが、クルマでのドライブという事を考えるのであれば、簡易トイレなどは車に常備しておいても良いものです。
冬の装備であれば、エンジンを止めても暖を取れる使い捨てカイロや毛布などもあると便利ですね。
[AdSense-kiji]
雪の日に駐車する際の注意点

車を駐車するタイミングで雪が降ってきてしまうことは十分に考えられます。
雪の日に駐車の際に気を付けておかなければならないことがいくつかあります。
注意点
ワイパーを立てる
雪が積もることが予想される場合に、長時間駐車するのであれば、ワイパーアームを立てるようにしましょう。
ワイパーの凍結防止という意味もありますが、フロントガラスから滑り落ちてきた雪の重みでアームが歪むことを防ぐ効果もあります。
サイドブレーキを引かない
駐車するときはサイドブレーキを踏むのが一般的ですが、これも雪が降る日には行わない方が良いとされています。
理由はサイドブレーキを作動させているワイヤーなどが凍結し、サイドブレーキが解除されなくなるためです。
では、どのように駐車すれば良いのでしょうか。
AT車であれば、Pレンジに入れるとミッション内でロックがかかる仕組みになっているので、これで駐車中のブレーキにします。
MT車の場合は、1速もしくはリバースにし、エンジンと繋げておくことで駐車中に動くことはありません。
エンジンをかけたまま駐車しない
車が埋まるほど雪が降ってくる状況でエンジンをかけたままというのは危険。
雪によってマフラーを遮られると、排気ガスが車内に逆流してしまい、一酸化炭素中毒による死亡事故につながりかねません。
車内において睡眠や休憩をとる場合には、燃料の節約という意味でも必ずエンジンを停止させましょう。
寒さ対策として毛布や使い捨てカイロなどを利用すると良いでしょう。
雪道の知識を持って備えよう

雪道のドライブに付きまとうリスクはゼロにはできません。
毎年雪道を走ることになる豪雪地帯のドライバーであっても、スタックやスリップ事故の全てを回避しているわけではないのです。
ゼロにはできませんが事前の備えや心構えでその被害を少なくなります。
スタッドレスタイヤは雪が降るシーズンには履き替え、スタックに備えてスコップの積み込みをしておきましょう。
スリップする可能性があれば、急激な操作はせずスピードは控えめにし、ドライブ前には降雪量や立ち往生などに関する交通情報の確認を行います。
言われてみれば当たり前のことですが、しっかりと実行した分だけリスクは減らせるのです。
まずは雪道に対しての知識を持って備えようという意識を持つことが大事なのです。
よく一緒に読まれてる記事は?